除夜の鐘の意味とは?起源や歴史も紹介

年の終わりにつく除夜の鐘。
なぜ、除夜の鐘をつくようになったかはご存知でしょうか。
そもそも除夜の鐘の「除夜」とはどういう意味なのか?
また、なぜ除夜の鐘は108回つくのか?
そういったことを紹介しますね。
除夜の鐘の「除夜」とは
まずは、除夜の鐘の「除夜」とはどういう意味なのか? ということなのですが、「除夜」は、1年の最後の夜という意味です。
除には、古いものを捨てて、新しいものを迎えるという意味があります。
1年が終わって、新しい年を迎えるから除夜は1年の終わりの夜、つまり大晦日の夜ということになります。
その1年の終わりにつく鐘が除夜の鐘ということですね。
なので、除夜の鐘は大晦日の夜に鳴らされるのです。
除夜の鐘をつく理由は?
なぜ、除夜の鐘をつくのか? といいますと、除夜の鐘をつくことで、人の心にある煩悩をはらうためです。
煩悩は、欲望や怒り、執着などの苦しみや憎しみですね。
こういった苦しみや憎しみの煩悩が百八つあると言われています。
煩悩の分だけ鐘をつきますので、百八回除夜の鐘を鳴らします。
百八回、除夜の鐘を鳴らすことによって、1年の煩悩を捨てることができ、新鮮な気持ちで新しい1年を迎えることができるのです。
そのために、除夜の鐘を百八回ついているのですね。
除夜の鐘の起源・歴史
除夜の鐘の起源は、中国の宋の時代(960年~1279年)です。
もともとは、鬼門を封じるために除夜の鐘をついていました。
鬼門は、鬼が出入りする方角のことです。鬼は丑と寅の間(北東)から出入りします。
これを月に直すと丑が12月で寅が1月になります。
つまり、12月と1月の間に鬼が出入りするので、それを封じるために除夜の鐘をついていたのです。
その中国の風習が鎌倉時代に伝来しました
除夜の鐘と同時に、臨済宗と曹洞宗という2つの禅宗も中国からもたらされました。
それから、仏教が大きく進歩して、様々な新宗派ができていったのです。
新しい宗派は、新しい寺の存在を知らせて、信仰を増やすために、布教活動が必要でした。
その布教活動に除夜の鐘も含まれています。
静かな大晦日の夜に、除夜の鐘を鳴らすことで、人々に知らしめていったのです。
そして、室町時代には除夜の鐘が広がり始めました。
江戸時代になると、一般寺院でも除夜の鐘をつくようになりました。
こうして、今でも除夜の鐘が受け継がれているわけですね。


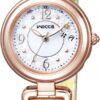


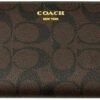

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません