鏡餅にみかん・裏白・ユズリハ・干し柿・するめ・昆布と一緒に飾る意味や由来は?

お正月に飾る鏡餅。
2段の丸いお餅の上にみかんを乗っけて、ゆずりはや干し柿、するめ、昆布などと一緒に飾りますよね。
これらの意味について、お伝えしますね。
鏡餅を飾る意味は?
まず、鏡餅を飾る意味なのですが、鏡餅を神仏にささげて、神様と人間をつなぐためです。
丸い形の餅を2つ重ねることによって、円満に歳を重ねるという意味があります。
鏡餅という名前の揺らしは、丸い形が昔の鏡の形に似ているからです。
鏡は、三種の神器で、天皇家が代々受け継いでいるひとつですね。
また、鏡には神様が宿るという言い伝えがあるので、お正月に飾るのです。
みかん
鏡餅の上には、本来、橙(だいだい)が乗せられていました。
子孫が代々続いて、繁栄するようにという願いが込められています。
ただ、橙は大きいため、小さめな鏡餅の上に乗せるのはバランスが良くありませんでした。
そこで、同じ柑橘類で小ぶりなみかんが鏡餅の上に乗せられるようになったのです。
裏白
裏白は、シダの葉です。
葉の裏側が白いので、裏白と呼ばれています。
裏白は、鏡餅の下に敷かれると思います。
白色は、清めの象徴ですので、裏白が鏡餅の下に敷かれます。
また、裏白は古い葉が落ちることなく、新しい葉が生えてくることから、永遠に栄えるという意味や、
左右の葉が対になっていることから、夫婦円満などの意味があります。
家族が仲良く栄えることを願うために敷かれています。
ユズリハ
ユズリハは木ですね。
ユズリハの葉を裏白の上に置かれます。
ユズリハは若葉が出た後に前年の葉が譲るように落ちていきます。
その様子が、親が子を育てているように見えるため、家が代々続いていくようにという意味が込められています。
干し柿
干し柿を串に刺した串柿を鏡餅に飾られます。
この干し柿を串に刺した形が三種の神器の一つである剣の形になることから、干し柿が飾られています。
また、柿は長寿の木であることから、長生きするようにという意味や、「嘉来(かき)」という言葉を当てて、幸せが来るという意味があります。
するめ
するめは、日持ちの良い保存食のため、幸せが長く続くという意味があります。
また、イカは足が多いことから、商売繁盛の縁起物としても、飾られています。
お金が足のように世間を渡り歩くことから、足は、お金の意味もあります。
昆布
昆布は、昔、広布(ひろめ)と呼ばれていました。
広布は広く一般に告げ知らせることから、祝いの日が広がって、喜びを広げるために、鏡餅と一緒に飾られています。




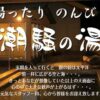

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません